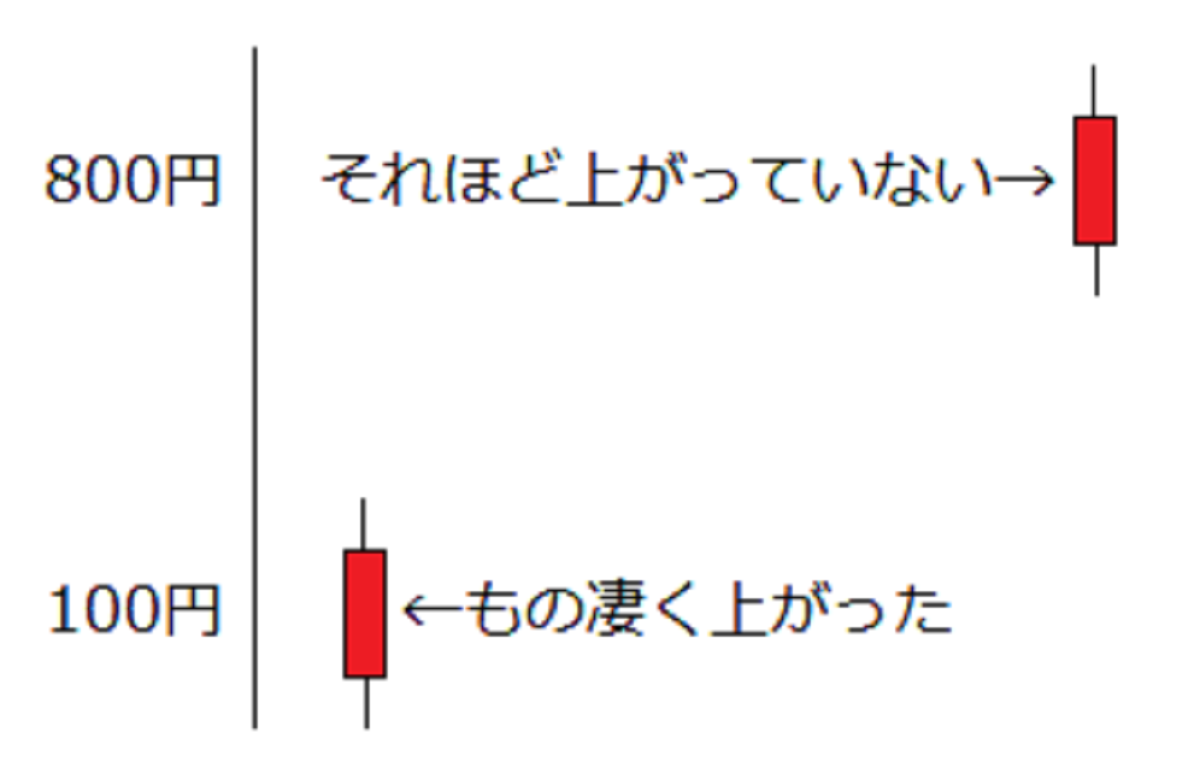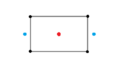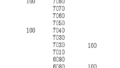私のポジションサイジング、すなわちロットの決め方、その計算方法とは?
計算の具体的方法
- 損失許容額を決める
- ポジション全体の金額を決める
- 分散銘柄数を決める
- 各銘柄の株数を決める
損失許容額を決める
明日、損をするとして、どのくらいの範囲に収めることができるのか?
これが当方、ポジションを持つに当たっての最大懸念事項であります。
利益ではなく、損失額。
利益なんざ、水もの。
儲からなくて当たり前だし、同値降りできれば御の字です。
それより、何より、損がまずい。
例えば、明日の損失は、最大5万円で済ませたい。
そう思えば、何がなんでもそれ以上はぶっこきたくない。
これが損失許容額を決める、と言うことであります。
この損失許容額5万円、これが決まったところで初めて、ポジション全体の保有額、すなわち金額が決まることとなります。
ポジション全体の金額を決める
明日想定される最大の損失許容額が5万円。
とするならば、ポジションの金額はいくらにすべきか?
当方の相場勘によれば、これに対応するポジション保有額は、80万円~100万円程度となります。
この場合、損失の率はいくらになるのか?
5÷80=0.0625
5÷100=0.05
よって、ポジション保有額に対する想定損失額の率は、5%~6.25%となります。
はっきり言いましょう。
明日、損してよろしい金額は、当方の場合、5~6%であります。
なぜ5~6%なのか?
これは経験則によるものです。
それ以上、損をしたら失敗もいいところ。
この感覚を念頭に、ポジション保有額を決定する習慣であります。
分散銘柄数を決める
ポジション保有額、すなわちトータルの金額が80~100万円と決まった次は、それをどのように分散するか。
もちろん、1銘柄投入でもよろしい。
しかし、当方の場合、分散できるのであれば、した方が良いと考えます。
相場には何があるかわかりません。
網は広く張った方がよろしいのであります。
すなわち、100万円を可能な限り分散したい。
ただし、各銘柄の保有額にばらつきがあってはなりません。
A銘柄は80万円、B銘柄は20万円、などと振り分けてしまいますと、A銘柄の動向により大方の損益が決せられることとなります。
しかし、どの銘柄が上がるか否かは、究極的な話、わからないのであるからして、均等に振り分けた方がよろしい。
そういう結論です。
したがって、2銘柄に振り分けるなら、50万円ずつとなりますな。
各銘柄の株数を決める
50万円ずつ2銘柄と、ポジションの振り分けが決まったところで、今度は各銘柄の株数を割り出すことになります。
例えば、
A銘柄の株価が2200円
B銘柄の株価が1200円
だとすれば、この場合、2銘柄に振り分ける株数は、
A銘柄 500000÷2200=227.2 より 200株
B銘柄 500000÷1200=416.6 より 400株
と言う結果になります。
これにて、100万円資金をA、B、2銘柄に振り分けての分散ポジション、その計算手順は終わりとなります。
当方、これを日々、日常的に行っています。
ポジションサイジングとは何か
当方にとって、ポジションサイジングとは、損をした時の影響を最小限にするためのもの。
一撃を食らわないよう、建玉の大きさを計算し設定することを意味します。
すなわち、儲かろうは10年早い。
それより何より、どうやって損失を避けるのか。
薄い損で逃げられれば、それで良しであります。
ポジション金額の2~3%マイナスで済ませること。
これを当方の用語で、微損と呼びます。
微損と言えども、痛いのですが。
ポジションサイジングとは、やむにやまれず、トレードを何とか微損で逃げるための手法です。
ポジションサイジングはスイングトレードの考え方か
通常、デイトレードでは分散ポジションを持たない人が多いでしょう。
1銘柄のみでデイトレードをする場合には、冒頭の手順の3番目の項目が省かれる形となります。
当方の考えでは、デイトレの場合にも、最大損失許容額からポジションサイズを割り出すのが合理的。
スイングでもデイトレでも、大元の考え方には変わりありません。
デイトレードにおいては、分散がやりにくい分、トレードの難易度は上がると言えます。
例えば、デイでは1銘柄集中、これに対し、スイングで10銘柄に分散。
この場合、時間軸において、スイングの方がよりねばれる印象が強い。
デイの1銘柄では、ねばるも何も、すぐ結果が出てしまうのであります。
相場勘>>ポジションサイジング
大事なことは、実は、ポジションサイジングよりも相場勘のほうが大事である、と言うことです。
上がる株を適切にセレクトできれば、ポジションサイジングは関係ありません。
下手だからこそサイジングが大事になってきます。
最初から損をする時のことを想定して、サイズを設定しているに過ぎない、と言う訳です。
相場勘が当たるなら、ポジションサイズなどどうでもよろしい。
すなわち、負けることが前提、その被害をどれだけ減らせるかと言う、実に厳しいお話。
これが相場の日常茶飯事であります。
つれーつれー。
本日の結果および雑感
さて、本日、大納会の結果は、デイ勝ち。
思わず手が出たリバ狙いの逆張り。
初心者時代と変わらないトレードしてますなあ。
こういうの、やめたいんですが。
思わず手が出る時はありますなあ。
とりあえず、2022年の相場もこれで終わり。
来年は何とか平穏無事にいきたい。
日本の地政学リスク、心配です。
それさえなければ、とりあえずよし。
バ●殿政治も我慢の範囲内です。
増税は極めてまずいですが。
経済を知らない官僚、政治家が多すぎ。
あるいは、わかっていても、言えないのかも知れませんが。
きっしーが、と言うより、その周りのブレーンみたいな人たち、どうにかなりませんかね。
その主張に対し、妙に納得してしまい、増税を受け入れてしまう筋も多すぎる。
政治家本人が束で「増税は国民の責任です」なんて、妙に強弁するのは笑うしかない。
江戸時代に帰れよ。
この状況、そう簡単に改善されそうにありません。
封建主義そのものです。
失われた30年の後に増税、これはある意味、記念碑です。
しかし、そのおかげで相場が下げればチャンスは来ます。
こっちは相場についていくしかありません。
でも、まさかリーマンショックみたいの、来ないですよね?
そんな寒い予感とともに、ノーポジ、新年へ。